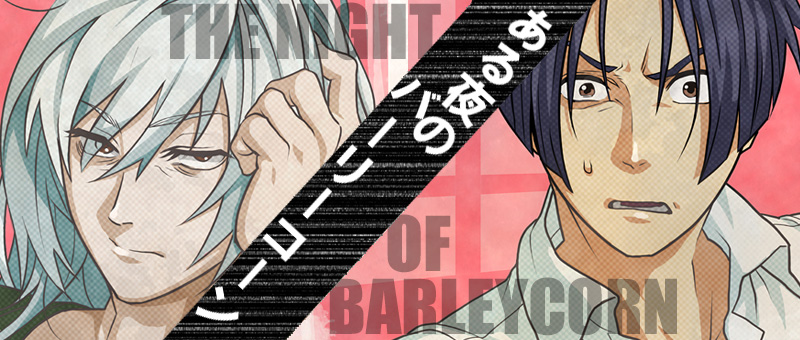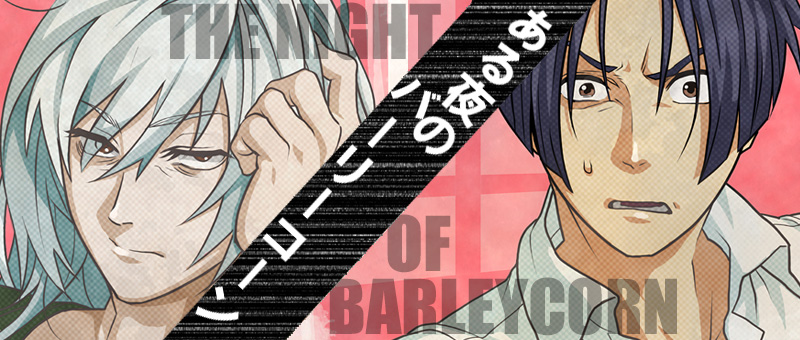明日起きることなんて、誰も分からない。いきなり火山が大噴火するかもしれないし、巡回中の人工衛星が役目をほっぽり投げて落ちてくるかもしれない。でも、普通そんなことは予測しないし、大体は、明日も同じような一日なんだろうと思うはずだ。明日のために時限爆弾でも仕掛けているのならまだしも、普段通りに振る舞っているならば、尚更。
だから――
「いい飲みっぷりだな! 次いく? 次」
「いきます!」
なんでこんなことになっているのか、さっぱり分からなかった。黒いラベルのフォアローゼスも底が見え始めているというのに、ノエミは陽気に注ぐ。それを受け取るのは、俺の彼女である、ポーリーンだ。
太陽は既に昇りきっていた。
初夏の風がカーテンを揺らしている。
「あまり飲むと、明日に響くぞ……」
「明日が何なの? 昨夜はお楽しみだったくせに? 私には酔っぱらう権利もないんだ?」
「お、お楽しみとか……」
ポーリーンは、ふん、と鼻を鳴らした。分かりやすく機嫌を損ねているが、それも当然に思える。だから余計縮こまった。人生の命運を握られている気分になる。たかが飲み会で、だ。
「そうそう、お楽しみだったな!」
「誤解を招く発言はやめてくれ!」
ノエミが膝を叩きながら豪快に笑っている。俺は青ざめた。横の方で、また笑う声がする。他に男が二人いるのだ。
「若いってイイよなあ、吸い取れないかね。吸血鬼みたいにさ、若いパワーをぐぐぐーっと。思うだろ?」
「トイレ……」
もう一人の男が、青い顔で立ち上がった。
「上品な言い方するなって、おまえついてんのか? 便所だろ? 便所で出すんだろ、ん?」
「Merde(くそったれ)」
青ざめた男が奥に消える。吐くんだろうな、と思った。
そう――ひとことで現状を示すのならば。
カオスだ。
この場には俺を含めて五人いる。けれどエラスムスのメンバーではなく、うち二人に関しては昨日知り合ったばかりだ。
目の据わったポーリーンが、酒気の帯びた語調で切り出す。
「――で、どうして私に連絡しないで、お友達集めて飲み会なんかしてたのか。聞かせて欲しいんだけど」
棘だらけだ。
俺だって聞かせて欲しい。
なんでこんなことになったんだ?
The Night of Barleycorn
ノエミはさっぱりし過ぎていた。同じアパートで暮らす面子の一人であるマリーアも、さっぱり系代表の女だったがそれ以上だ。
というより、ノエミには女らしさを感じない。感じろという方が無理なくらいだ。化粧気はもちろんないし、程よく筋肉のついた肉体は、中性的だった。何といっても髪型。一か月前までインドでバックパッカーをしていたらしく、丸坊主に近かったのだ。出家でもしたのかと思ったが、単純に、女という理由で襲われないためらしい。しかしイヤイヤではなく、ノリノリっぽかった。彼女は愉快そうに坊主の利点を上げて、周辺の女に布教しようとしていた。もちろんヒかれていたが。
「ハーバルエッセンスとかケラスターゼとかさあ、意味わかんないだろ? 髪がツヤツヤじゃないとパリを歩けないって思ってんだ。坊主だってパリは歩けるぞ」
彼女は教室でふんぞり返りながら、そう言ったことがある。俺は困りながら、確かこう言った。
「綺麗な髪に越したことはないだろう?」
「髪の重要性って何だ? そんな必要なもんか?」
「重要性って言われたら……、ああ、ほら、頭を守る機能」
「なるほど、そっちは一理あるな」
彼女はにやにやしていた。それ以降も彼女はほとんど坊主のままだった。けれどたまに帽子を被ってみせて、俺を見ると、「防護だ」と言った。笑うしかなかった。
そのノエミとは、哲学の講義で何度か一緒になった。坊主頭に哲学が入り込むのか疑問でしかなかったが、他にはない信念はあるんだろうと思う。彼女に比べて俺は当たり障りのない男だ。そんな存在を目指している節もある。ノエミにとってはつまらない存在だろうと思っていた。
彼女が講義に顔を出すのも稀だった。何をしていたか聞くと自転車で行けるとこまで行ってみたとか、地元の中学生に混じってサッカーをしていたとか、訳の分からない発言が出る。
きっと、面白くて、刺激のある光景を、追い求めているんだろう。ちょっとそこまで、と言って宇宙を目指しても、俺は納得する。実際インドに行ったときは、前日に思いついたという話だし。夢にシッダールタが出てきたらしい。俺はそいつの顔なんか知らない。
だからノエミの瞳に俺が入り込んだ時、何か裏があるのではと疑ってしまった。しかし同時に、好奇心に負けてもいた。
もしかしたら、彼女に無茶苦茶にされたかったのかもしれない。今思うと、だけど。
ノエミは俺を夕飯に誘った。
なぜ俺なのか、問いかける余裕はなかった。「インドカレーでも食べにいくのか?」そう聞いたとき、「ところがな、フランス料理屋だ。夢にナポレオンが出てきた」と答えられた。俺はやっぱり意味が分からなかった。
女に見えない相手だけど、性別上はやはりそっちだ。だから、ポーリーンも誘っておこうと思った。黙って女と食事に出掛けたとなれば、たとえやましいところが無くとも、機嫌を損ねるかもしれない。火のないところにも煙がたったりするのだ。俺は恋人に、「夕食の予定ある?」と携帯からメッセージを送った。けれどポーリーンは、女友達と予定があるのだと返してきた。聞いてもいないのに誰と行くのか列挙したメッセージだった。俺は「分かった」とだけ打って、ノエミと出かけることにした。
本当は俺も、ノエミの名前を出すべきだった。
……やはり、火はあったのだろうか。
◇◇◇
「うーす、ちーっす」
待ち合わせに現れたノエミは、おんぼろのスクーターに跨っていた。既に黒い排気ガスが吐き出されている。嫌な予感がした。彼女は、足を用意してくるから待ってろ、と俺に言ったのだ。
「……二人乗りか」
「十年来の相棒だよ、心配するなって」
「メンテナンスには出しているんだろうな!」
「そこらの軟弱バイクと一緒にすんな!」
「あのな……!」
長く一緒に過ごしているポーリーンにさえ、こんな突っ込みをしたことはない。急激に全身の力が抜けていった。
「一応聞いておきたいんだが……」
「言ってみ。メンテナンス日以外で」
「……ちょっとそこまで、のノリで、そいつでパリを目指したりしないよな」
やりそうな気がしていた。もし頷いたら、帰ろうと思った。
「まさかあ、途中で腹減って死んじまうよ」
「よかった」
彼女はヘルメットを投げた。受け取って、どうか途中で故障しませんように、と祈りながらスクーターに跨る。思った以上に順調に走りだし、ストラスブールの小道を抜けていく最中、こいつは言った。
「ちょっとメッツまで」
「えっ?」
一瞬、どこか分からなかった。それが、都市のひとつ「メス」のドイツ語的な呼び方だと気づくのに、数秒かかった。ノエミはストラスブールの産まれで、時折ドイツ語らしい発音をする。自然にそうなるのかもしれないし、わざとやっているのかもしれない。
と、冷静に分析したところで――
「やめろおおおお!」
俺は叫んでいた。
ストラスブールからメスまでは、150km近くあるのだ。
ノエミの大爆笑と、おんぼろスクーターの死にそうな呻きが、耳にこだました。
◇◇◇
結局、メス方面に80km近く走って、途中の町でスクーターは止まった。おんぼろの癖にかなりのスピードが出ていた。一時間も掛からなかったと思う。
メスに行くのは冗談だったらしく、目的地となったのは名前も知らない辺鄙な町だ。どうやらここに、彼女がよく行く上手い料理屋があるという。店は町の中心からも離れていて、人気のない離れにあるのに、路肩に車がたくさん連なっていた。
「ほんとマジ有名なんだって、ベッコーフが最高」
ベッコーフはアルザス地方の名物料理だ。壺みたいな食器にぶちこまれる具だくさんのスープ、といったところだろうか。ノエミは背中を掻きむしりながら店の扉を潜った。
大盛況だった。一体どこからこんな人の群れが現れたのか、と思うほど、外の世界と違っている。分かりやすく大衆食堂の様相だった。机は程よく密集していて、店員が忙しなくあっちへこっちへとオーダーを取りに回っている。レジにどっしりと構えた中年の男に、ノエミは「よっ」と声を掛けた。知り合いらしい。
「ここで働いたことがあってね、死ぬほど忙しいけど、ただ飯のクオリティは最高だよ」
不思議そうにした俺に、先回りして説明してくれた。俺とノエミは奥の席に案内された。二人掛けのテーブルなんてものはなく、相席だった。常連客向けの食堂は、メニューらしきものが置かれていない。今日あるものを店員に聞いて、注文するのだ。
「さー、遠慮せずにじゃんじゃん注文しよう! 大丈夫、割り勘だから!」
「別に、出すつもりでいたけどな……」
「何それ、きもいぜ……男が女に払うもんっていう、君みたいな考え大嫌いだ」
じゃあなんで俺を誘ったんだ。
本当に意味が分からない。
頭痛を感じ始めた頃、ふと、隣の声が耳に入った。俺とノエミはもちろんフランス語でやり取りをしているし、店の中も同じようにフランス語で溢れ返っているというのに、聞こえたのは英語だった。だからだろう、少しだけ気になってしまった。
横目で相席者を伺うと、二人連れの男たちだった。
そいつらを見た瞬間、この席が外れだと直感した。雰囲気が圧倒的に違うのだ。何というか、普通じゃない。言語や身なりとかじゃなく、醸し出すものが違う。対面――つまりノエミの隣にいるのは、長い髪の男だ。顔立ちは整っている癖に、目があまりにも死んでいる。更に、ぴくりとも表情を動かさないでいるものだから、不気味さに拍車がかかっていた。
恐る恐る俺の隣にいる男も伺う。痩せこけた男で、眼窩に影が出来ている。髑髏みたいだと思った。短く髪を刈り上げている所為で、頬骨の陰影もくっきりと分かる。髪の長い男とは対照的に生気に満ちた瞳をしていたが、逆に飢えた獣みたいにぎらついている。唇の端をわざとらしく持ち上げる笑い方をしていた。どちらの男も、顔色がすこぶる悪い。絶対、堅気じゃないと思った。
「だからなあ、いい加減、おれたちは次のステップに行くべきなんだよ。分かるか? 分かるだろ? 上の要望なんか聞いてちゃ、ためにならないぜ。人類の進化を握れるかもしれないんだ」
髑髏男が言う。
人類、進化と来たか。
よく見積もって研究者、悪く見積もってカルト宗教、普通に考えて比喩表現の豊かな男、といったところだろう。喋るのはこっちの方で、髪の長い方は基本的にだんまりだった。
「無能は捨て、有能を残す。そいつを繰り返して、遺伝子に学習させてやるのさ。分かるだろ? 淘汰だ。やがては無能が排除されていく、自動的にな。スバラシイ世界の出来上がりだよ!」
「貴方の選択基準を活かしたら、サイコしか残りませんよ」
髪の長い方が口を開いた。案の定、陰鬱な声をしている。聞き取り辛い発音だった。
「おまえの方が十分サイコだよ、ロリコンが」
「…………」
「おい、ポテト食うか、嫌いなんだ」
「もらいます」
関わらないようにしよう。
俺は強く誓った。
だが、その矢先だ。
「おいおーい、男二人だけ? シケてんなー、一緒に呑むか?」
注文を終えたノエミが、二人に声を掛けた。
ほんと、もう、勘弁してくれよ。
俺は心の中でぐったりと呟いてから、断れ、頼む、と二人連れに念じもした。
が――、
「ワインは白か? おれはリースリングしか飲まないんだ」
「私は何だって飲む、アルコールならね」
髑髏男が身を乗り出して、提案にのってしまった。
ノエミの性格を思い出す。そうだ、こいつは愉快そうな世界に飄々と足を突っ込んでしまう。俺には愉快でも面白くもない、避けたいばかりの二人連れも、ノエミにとってみたら開拓地に違いない。未知の領域が大好きな奴なんだ。
「ようし、じゃあボトルを頼もう。おれは立派な社会人だからな、それくらい奢ってやるさあ。おまえヒッピーか何かだろ」
「ちげーよ大学生だっつの、天下のストラスブール大学だっつの」
「うそつけ」
スムーズに会話に入りだした二人を眺め、ため息を殺す。視線の置き場に困って、黙ったままの長い髪の男を見た。
そいつは俺を凝視していた。
ぎょっとする。
無表情の男が俺を見つめているのだ。恐ろしいに決まっている。そいつはたっぷり数秒俺を見てから、視線を横へと逸らした。唾を飲み込んで、意を決して声を掛ける。
「どこかで会いました……?」
返答をくれなかった。
何か言えよ馬鹿野郎、と思った。
◇◇◇
意外――でもないかもしれないが、ノエミと髑髏男は意気投合してしまった。髑髏男の名前はトマゾといって、ミラノ出身のイタリア人だった。ヤコポを連れてくれば良かったと後悔する。勝手に喧嘩しだして険悪なムードを作ってくれるだろうから。髪の長い無口な男は、ミシェルといった。こっちはフランス人だ。トマゾがフランス語を得意としていないようで、俺たちは英語で話した。
彼らはメス郊外の工場で働いているらしい。何の工場かは教えてくれなかったが、パン工場だとか平和なものじゃない気がした。クスリを扱ってなければいいんだが。
料理は最高に旨かったが、俺は気分が悪かった。変な二人が横にいるからじゃない。俺を誘った癖して、ノエミがトマゾに夢中だからだ。
でも――、俺はノエミと話がしたかったんだろうか。
そうじゃない気がする。多分、ノエミの見る世界に興味があったのだ。そして、変わり者である彼女の光景に俺が入り込んで、子供みたいに優越感を抱いたんだろう。けれど、今の俺は、彼女の世界にいなかった。
俺は黙々と料理を口に放り込みながら、それなりに悩んだ。変わった奴に興味を持たれるというのは、悪い気がしないものだ。それだけの感情だと言い聞かせながらも、声を潜めて話しかける。
何となくフランス語にした。
どうせミシェルは分かるだろうが、こいつは度外視していい。だって、俺とノエミの話に関心なんて持たないだろう。
「ノエミ、ちょっと」
「ん?」
彼女は、くっとワインを飲み干した。いい飲みっぷりだった。
「なんで、俺を夕食に誘おうと思った」
誘われた時は、聞くまいと思っていた。それを、こんな時に限って取り出す。
「第六感」
「は?」
ノエミは事もなげに言った。
「夢にイエスキリストが出て、お告げしたんだ。今日はこいつと出かけると、おもしろいことあるぞーって」
「……キリストは嘘だろう」
「ああ、嘘だよ」
いたずら小僧みたいな笑みだった。
「第六感は」
「そっちはほんとだな。冴えるんだよ。鼻がいいのかな? 面白そうな未来を連れてきそうなやつをね、当てられるんだ」
「無茶苦茶だ」
「本当さ。実際、愉快だろ? こいつら絶対堅気じゃないぜ」
「……それ、俺じゃなくても結果は同じじゃないか?」
「それがね、多分、違うんだな。君と出かけなかったら、奥の席に行けなかった。そういう風になってる」
「……無茶苦茶だ」
ノエミは鼻でふふんと笑った。それからまた、「本当さ」と言った。予言者みたいだった。
「おい、おい。やめろ、フランス語はやめろ、おれに分かる言葉で話せ。おいミシェル、通訳しろ」
機嫌を悪くしたトマゾが入り込んでくる。そいつの対面で、死人みたいな男が瞬いた。それから、肩を竦めた。
「痴話げんか」
「違う!」
反射で突っ込みを入れたのは俺だ。
「カップルじゃないのか? なんだ、そうなのか? おれがノエミに手を出してもいいのか?」
「おっとトマゾさん、変わりもんだな」
ノエミが爆笑を堪えるように、引きつり笑いを起こしている。変わりもんだなって、自分で言ってしまうのか。
俺はもう一度、ノエミに聞いた。一応、英語に変えておいた。トマゾが面倒だったのだ。
「……本当にそれだけ?」
「それだけ、だけど?」
ほかに何か? と言いたげな目だった。俺は首を横に振った。なぜだか、ひどい倦怠感を覚えた。力が抜けていく。
これは――なんというのか。
いや、認めることが出来る。
俺はがっかりしていたのだ。
俺に何か特別な理由があって、特別な存在感みたいなのがあって、ノエミの目に留まったのかもしれないと、そう思っていたのだ。
なんだ、思い上がりか。
俺が勝手に落胆しているのも、ノエミは見ていない。俺に何かがあって彼女が声を掛けたんじゃない。言うところの、第六感に従っただけなのだ。俺はこの二人に会うためのきっかけでしかなかった。
だが、考えると、それが当たり前だ。
恋人の顔色ばかり伺っている俺は、ふと思い立ったからと言ってインドに旅立つこともない。ポーリーンが嫌がるだろうから、坊主にすることもない。
俺であるアイデンティティはないのだ。
この、ネインというあだ名だって。
俺はどこにもいない。そういう存在だ。
彼女の機嫌を大きく損ねた瞬間、俺は家族ごと消滅するかもしれない。いや、実際のところ、それは思い込み過ぎだとも思う。ポーリーンは優しい女だ。一度も、脅された試しはない。
しかし――
勝手に想定してしまう。彼女の圧力を無意識に感じ取ってしまう。無償の愛を捧げなくてはならないと信じ込んでしまう。
家のため。親父の仕事のため。
俺は無になる。
……そんな男に、ノエミの言う面白い世界は有り得ないだろう。
少し、嫌になってくる。
別にこんなことくらいで、気落ちする自分じゃない。子供の頃からポーリーンと付き合って、気づけば彼女のために生きていた。今更自分の存在が認められないからと言って、嘆く理由もない。
それでも俺は人間だし、うんざりしたり、胸が締め付けられてしまう時もある。今がそういう感じだ。
ため息を殺して、立ち上がった。自然になるように心がけて、声を掛ける。
「煙草、吸ってきていい?」
「メシの最中に煙草か、いい度胸だなー」
そうは言っているが、ノエミは怒った様子じゃなかった。普段、煙草なんて吸わないのだが、ヤコポの付き合いで味は覚えていた。あの男は寂しがり屋だから、一人でベランダ族になるのが嫌なのだ。
俺が席を離れようとした時、意外にも、死人――じゃなかった、ミシェルが立ち上がった。
「……吸ってきます」
「いい度胸が二人だ」
そう返したのはノエミではなくトマゾだった。仲良しアピールみたいで、若干いらっとする。しかしそれも一瞬だ。
これは連れ煙草か? 俺はヤコポみたいに、ひとりで吸うのが寂しいタイプじゃない。訳が分からなかった。
表情のない男を横目で見る。
大麻はやめてくれよ。
一応違法なんだから。
◇◇◇
店の喧噪から一歩離れると、世界が変わった。入るときもそうだった。扉という分かりやすい境界線から抜け出ると、夜らしい静寂に包まれる。
店の壁沿いを少し行って、振り返る。あいつがどうするつもりなのか、気になる――というより戸惑っていた。
夜の気配に包まれたミシェルは、そのまま消えてしまいそうだった。まだ若いのに灰混じりの髪をしていて、それだけなら夜でも目立ちそうなものなのに、存在を感じない。まるで亡霊だ。
俺はひょっとして、生きた人間を相手にしてないんじゃないか? あのトマゾだって、悪霊の類かもしれない。ゴーストどもだ。案外、妄想じゃないかもしれない。
煙草を指で挟みながら、伺うように言う。
「吸いますか、とりあえず……」
すると彼は緩慢な仕草で首を傾け、俺の方を見た。やはり表情が薄い。が、その瞬間、片方の眉がすっと持ち上がるのを見た。
もしかして……。
「なぜ、隣り合って吸う必要が?」
こいつは外に出たかっただけで、別に、俺と連れ煙草なんてするつもり、なかったんじゃないか?
「いや、一緒に出てばらばらにっていうのも、何か、おかしいだろう。嫌なら別に……」
「……構いません」
ミシェルはため息をついたようだった。
どうして俺がこいつと一緒に煙草吸いたい、みたいになってるんだ? ため息をつきたいのはこっちだ。
店の中でも外でも、やるせない思いばかりだ。もう面倒になった。半ば投げやりになって、壁に背を預ける。きちんと一人分の距離を開けて、ミシェルは俺の隣に来た。
俺は普通の、どこでも手に入るボックスの煙草だったが、ミシェルは巻き煙草だ。紙に草を乗せて、くるくる巻いて、唾液でくっつけるってやつ。本当に大麻じゃないだろうな? 嫌な予感しかしなかった。
ライターで、彼の手元が照らされる。そこで初めて気づいた。手首に走る痕跡。めくれ上がった皮膚が融合できずに、傷として残り続けている。
ああ、つまり、そういう……。
不憫だとか、可哀想だとは思わなかった。この男なりに悩むことがあって、苦しんだ末に、手首を切る決意をしたんだろう。しかし第三者から言ってみれば、そんなもの、隠しておいて欲しい、といったところだ。
俺は見て見ぬ振りを決め込んで、煙草に火をつけた。
だが、思い切り煙を吸い込んで、吐き出した瞬間、言葉までもが漏れていた。
「……隠せ、少しは」
「……は?」
俺は何を言っているんだ?
突っ込んでいい問題じゃない。他人の話だ。大体手首の傷なんて碌なものじゃない。この男が、自分で地雷だと主張しているようなものだ。そんな話題に触れて、まともな会話など出来るはずがない。俺は自分の失言を呪った。
……自覚している以上に、俺は不安定になっていたのか?
「手首の……傷だ。お前はそれでいいかもしれない、でも、他人のことも考えてくれ」
言ってしまったからには、続けるしかなかった。
「勝手に見たって言われたらそうなるが……、そういうのって、目を引くもんだろう。お前の友人は何とも思わないかもしれない。でもそういう奴らばかりじゃない。つまり……だから……」
ミシェルは何も言わない。
少し考えてみれば、俺の方がおかしいと思った。さっき知り合ったばかりの、年上の男に、いきなり説教をかましている。
「だから……俺の気分が悪いんだ」
最初はいらだっていた癖に、最後は、申し訳ない気分になっていた。伺うように彼を見る。じっと、手首を見つめていた。
「彼女は……隠しているのですか」
「え?」
彼の口から漏れたのは、理解できない言葉だ。彼女? 誰を指している? ノエミか? あいつは手首に傷なんてない。いや、そもそも、どこかに傷があったと仮定しても、なぜこいつが知っている?
それに――どうして、そんな――
苦しそうな声で言ったんだ?
「いえ……、気にしないでください」
「気にするな、って……」
彼はまた黙り込んだ。ふたつ分の煙草の灯が、ちりちりと揺れている。吸い込む度に蛍のように明滅する。
「やましいもの、か」
消えそうな呟きだった。ミシェルを見る。
俺は続きを促そうとした。
「そう言いたかったのでは? 隠す必要のあるものだと」
「やましいか、やましくないかは分からないが、少なくとも――」
「他人の気分を害する」
「……ああ」
「気が回りませんでした。……他人を意識する必要がないもので」
お互いに、二本目の煙草に火を点けていた。
「どれだけ閉鎖的な職場なんだ……?」
「職場の問題ではない」
……つまり、自分が閉鎖的な人間だと自覚しているのか。それを良しとしているのだろう。別に、とやかく言うつもりはない。手首の傷は隠して欲しいが、性格は個人の問題だ。職がある事実に驚きを隠せないが。
だが――、
「許されるのか、それで。人に何か言われたりしないのか」
「何か?」
「だから……こうした方がいいとか、ああだとか……」
ミシェルはまた、眉を動かした。それから双眸も細めた。彼なりに不機嫌を表現したのかもしれない。
「昔はね、言われましたよ。……今は、やることをやるだけです」
「そう、か……」
「貴方は、拘りますね。許されない人ですか」
一瞬、ひやりとする。
どんな方向性であれ、自分そのままを押し出せない俺が、ミシェルの言葉に怯えたのだ。
だが……そのままの自分など、とうに見失った。既に、何がなんだか分からなくなっている。ここにいる男はポーリーンの望む恋人でしかない。
逃げ道を探して、矛先を変えようとする。
「どんな工場なんだ」
「職場の問題ではないと言ったはずです」
「……気になっただけだ」
彼は煙草を放り捨てた。暫く、間があった。表情はやはり変わらず、何を考えているか、まったく分からない。
「私のジョークと、彼のジョーク、どちらが良いですか」
「え?」
きっと、怪訝な顔をしただろう。
どっちにしたって本当のことは教えてくれないのか。そう言おうとしていたのに、馬鹿正直に選んでいた。
「じゃあ、お前の……」
感情の読めない瞳が俺に向かう。それから、形ばかりが整った、陰鬱な声しか吐き出さないその唇が、ほんの少し笑みに変わった。それ自体がジョークみたいだった。
「人を作っているのです」
凍りついた。
「ジョークですよ」
ミシェルは背を向けた。俺の煙草も、もう終わりに近かった。指先に熱を感じ始めて、慌てて放り捨てる。
嫌なジョークだ。手首に傷を持つ、死に損ないのような男が言うから、尚更不気味になる。
「お、おい……待ってくれ。……あいつのジョークも教えてくれ」
本当にジョークなのか――そんな疑念すら抱いてしまう。
ある訳ないと思っているのに、漠然とした形のないものが、俺の背を撫でる。多分、それを、恐怖というんだろう。
「そんなに愉快でしたか。私は冗談のセンスがないはずです」
「いいから――」
うすら寒いものを感じながら、もうひとつのジョーク……いや、情報を聞き出したかった。彼らが何者なのか、その欠片でも知りたいと思った。
ミシェルはため息をついた。
「大人の玩具工場です」
それきり、さっさと店に戻ってしまった。
残るのは夜の気配だけだ。
「……はあ?」
俺は力が抜けていた。
|